
昔は身近、今は希少
ラタン家具の価値を見直す
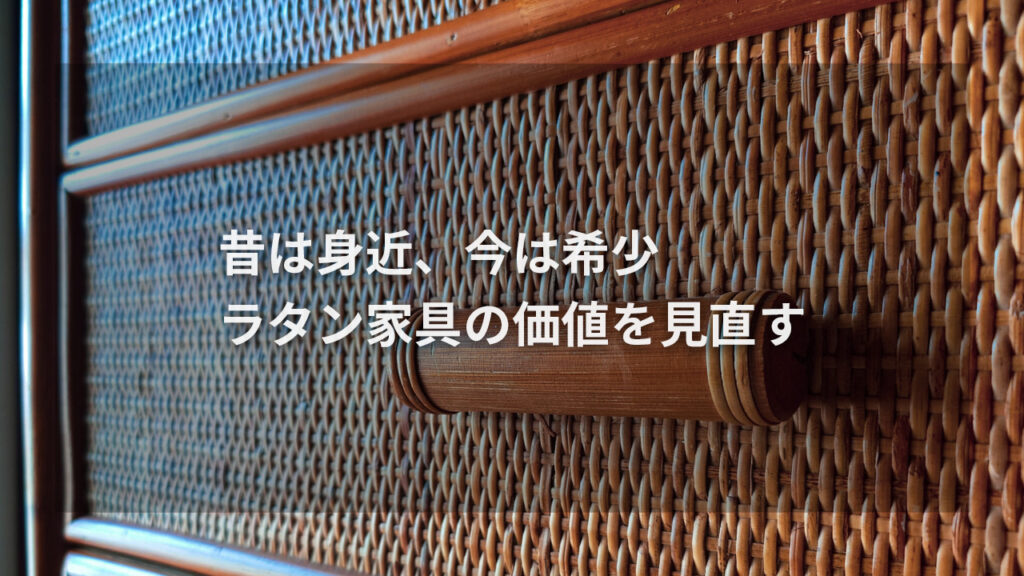
最近の暮らしの中で、自然素材を取り入れたインテリアに注目が集まっています。
木や布、陶器と同じように、ラタン(籐)の家具もそのひとつ。編み込まれた表情からは軽やかさが伝わり、触れるとほんのり温かみを感じます。
どこか懐かしいのに、今の住まいにもすっと馴染む不思議な存在感があります。
かつてはどこの家庭にも当たり前にあったラタン家具ですが、今では希少な素材となり、その価値が改めて見直されています。単なる「昔の家具」ではなく、エコや快適さ、そして長く使える安心感を持つ家具として、ふたたび注目されているのです。
この記事では、ラタン家具の素材としての特徴や歴史、今の暮らしに合う魅力、そして選び方のヒントまでを家具屋の視点からご紹介します。読み進めるうちに、きっとラタンが持つ奥深さとやさしさを再発見していただけるはずです。
1.ラタンとは?|自然が育んだしなやかな素材
ラタン(籐)と聞くと、どこか懐かしい響きを感じる方も多いのではないでしょうか。昔はどの家庭にも、編み込まれた椅子やカゴがあり、自然の風合いが暮らしの中に溶け込んでいました。
ラタンは、東南アジアの熱帯雨林に自生するヤシ科の植物で、木ではなく、つる性でぐんぐんと伸びていく生命力にあふれた素材です。細く見えて驚くほど強靭で、同じ太さの木材に比べても折れにくいのが特徴。家具として形を変えても、そのしなやかさと強さは失われません。
ラタンの魅力は、自然が生み出したしなやかさにあります。繊維が長く、柔軟で、曲げても折れにくい性質を持つため、曲線を活かしたデザインの椅子やテーブルにも適しています。これによって、軽やかな雰囲気と柔らかさを同時に持ち合わせた家具が生まれるのです。
また、内部に空気を多く含むため軽量で、持ち運びも楽にできます。掃除のときに椅子やラックを少し移動させたいとき、ラタンの軽さは何気ない暮らしの快適さにつながります。
さらに、ラタンは湿度の高い地域で育つ素材です。日本の梅雨や夏のように湿気が多い環境でも傷みにくく、通気性に優れているので、蒸れやカビを防ぎやすいのも安心できる点。
自然素材でありながら、湿気に強いという性質は、毎日の生活に寄り添う家具として頼もしさを感じさせます。
私たちの暮らしは、便利さや新しい素材の登場とともに変化してきましたが、自然素材ならではの温かみや、長い時間をかけて育まれた素材が持つ安心感は、やはり格別です。
ラタン家具はその代表的な存在。手で触れたときの素朴な感触や、編み目からこぼれるやわらかな光は、人工素材では真似できない魅力です。
近年は海外でも資源が減少し、ラタンはかつてより希少な素材になりつつあります。
だからこそ、今あらためて「自然が育んだ素材の力」に目を向け、暮らしの中に取り入れる価値があるのかもしれません。
2.昔はどの家にもあったラタン家具の歴史
少し前の時代を思い返すと、ラタンの家具はとても身近な存在でした。
昭和の頃、多くの家庭の縁側や居間には、編み込まれたラタンの椅子やテーブル、収納棚が当たり前のように置かれていました。
軽くて動かしやすく、風通しのよい編み目から涼しさが感じられるため、夏の暮らしにぴったりだったのです。団扇や蚊取り線香と同じように、ラタン家具も「季節を感じる暮らしの道具」として親しまれてきました。
当時のラタン家具は、今のように「特別なもの」という印象ではなく、もっと手軽に手に入る日用品に近い存在でした。価格も比較的安価で、量販店や街の家具屋に行けば、手頃なラタン製のチェアやラックが並んでいたものです。
どこか懐かしい雰囲気の編み込み模様は、多くの家庭にとって「暮らしの景色の一部」だったといえるでしょう。
しかし時代が進み、住宅様式やライフスタイルが大きく変化すると、ラタン家具は徐々に姿を消していきました。
和室からフローリングのリビングへ、扇風機やエアコンなどの家電が普及し、暮らしの中心にあった「涼をとる工夫」が求められなくなったことも背景にあります。
その結果、軽やかで涼しげなラタン家具は「どこの家にもあるもの」から「一部の人が選ぶもの」へと変わっていったのです。
ところが近年、ナチュラルな素材や環境に配慮した暮らしが注目されるようになり、ラタン家具は再び見直されつつあります。
昔ながらの懐かしさを感じさせながらも、現代のインテリアに合うデザインに進化した製品も多く登場しています。過去に「ありふれた存在」だったラタンが、今は「価値ある素材」として再評価されているのは、とても興味深い流れです。
暮らしの道具として当たり前に使われていた時代と、希少性を帯びた今。ラタン家具の歴史を振り返ると、私たちの生活の移り変わりが自然と浮かび上がってきます。

3.今では希少に|ラタン素材の現状と価格の変化
かつて手軽に買えたラタン家具ですが、近年では「少し高価な家具」という印象を持つ方も多いのではないでしょうか。その背景には、ラタン素材そのものが世界的に減少している現状があります。
ラタンは東南アジアの熱帯雨林で育つ「つる性植物」で、インドネシアやフィリピン、マレーシアなどが主な産地です。
しかし森林伐採や農地開発の影響で自生地が減少し、採取量は年々縮小傾向にあります。
たとえば、世界最大の産地であるインドネシアでは、1990年代に比べて天然ラタンの供給量が大幅に減り、現在では人工的に管理されたプランテーションでの栽培に移行するケースも増えています。
かつては農村部の副業として広く収穫されていたラタンが、今では限られた地域資源になりつつあるのです。
こうした資源の減少は価格にも直結しています。
日本国内の家具市場においても、昔は比較的安価に出回っていたラタン製品が、今では輸入コストや加工コストの上昇も重なり、以前の2倍以上の価格帯で販売されることも珍しくありません。
例えば、昭和の頃は数千円で買えたラタンのスツールが、現在では数万円するケースもあるほどです。
また、労働環境や国際的なサプライチェーンの変化も影響しています。
東南アジアの現地職人が一つひとつ手作業で編み上げるラタン家具は、大量生産が難しいため、どうしても希少性の高い製品となります。
結果として、安価に見える「ラタン風」のポリプロピレン製品が市場を広げ、本物のラタンは「自然素材の価値を大切にしたい人が選ぶ家具」として位置づけられるようになっています。
こうした背景を知ると、今のラタン家具の価格の高さにも納得がいくのではないでしょうか。
単なる値上がりではなく、素材が減り、手間がかかるからこそ生まれる価値。そのことを理解して選ぶと、家具はただの生活道具ではなく、自然と人の手が生み出した「特別な存在」として、暮らしの中で長く愛着を持って使えるものになるはずです。
4.軽くて丈夫、湿気に強い|ラタン家具の特徴
ラタン家具が長く愛されてきた理由のひとつは、その「軽さと丈夫さ」のバランスにあります。
ラタンは細く見える「つる性植物」ですが、繊維が強靭でしなやかに伸びるため、同じ太さの木材よりも折れにくい特性を持っています。そのため、軽量でありながら驚くほどの耐久性を備えており、日常使いの椅子や収納家具に適しているのです。
軽さは暮らしの中で大きな利点となります。掃除の際に家具を移動させたり、模様替えをしたりするときも、ラタンなら片手で持ち上げられるほど。力の弱い方や年配の方にとっても扱いやすく、「家具が軽い」ということは暮らしやすさに直結します。
さらに、ラタンは湿度の高い環境で育った植物です。
そのため日本の梅雨や夏の蒸し暑さにも強く、湿気を含んでも腐りにくい性質があります。編み込まれた構造は通気性に優れ、座ったときの蒸れを防いだり、収納品をカビから守ったりする役割も果たします。自然素材でありながら湿気に強いという点は、日本の気候と非常に相性が良いといえるでしょう。
このように、軽さ・丈夫さ・湿気への強さを兼ね備えたラタンは、日々の暮らしを快適にする実用性にあふれています。見た目の涼やかさだけでなく、暮らしに寄り添う素材としての頼もしさこそ、ラタン家具が今もなお選ばれる大きな理由です。
5.海外での生産とラタンが減少している背景

ラタン家具の原料となるラタンは、主に東南アジアの熱帯雨林で採取されています。インドネシア、フィリピン、マレーシアが三大産地とされ、特にインドネシアは世界のラタン供給量の約7割を占めてきました。
しかし近年、この供給体制は大きな変化を迎えています。
背景には森林資源の減少があります。
農地開発やパーム油プランテーションの拡大によって熱帯雨林が伐採され、ラタンが自然に育つ環境が急速に失われているのです。国際熱帯木材機関(ITTO)の報告によれば、天然のラタン資源は過去30年で半分以下に減少した地域もあり、天然採取だけでは需要をまかなえなくなってきています。
そのため現在は、人工的に管理されたラタンのプランテーションでの栽培が進められていますが、ラタンは成長に時間がかかるため、すぐに供給量を回復させることはできません。
一般的に、家具に使用できる太さになるまでに7〜10年ほど必要とされ、木材と同様に「育てる時間」がかかる素材なのです。
さらに、現地の労働事情も影響しています。
ラタン家具は一本一本を人の手で裂き、曲げ、編み込む工程が欠かせません。自動化や大量生産が難しく、熟練職人の技術に依存しています。
しかし都市化の進行で若い世代が農村部から離れ、職人の数が減っていることも、供給不足と価格高騰の要因となっています。
こうした事情から、現在の市場では「ラタンそのものが減っている」という資源的な希少性に加え、「生産に携わる人の減少」という人的要因も重なり、昔のように安価で豊富に手に入る素材ではなくなっています。
その一方で、プラスチックや金属と比べて再生可能な自然素材であることから、欧米を中心にエコ意識の高い人々に再評価されており、需要はむしろ高まる傾向にあります。
つまり、ラタンは「資源としての限りある存在」でありながら、「持続可能な素材」として注目されるという二面性を持つ素材になっているのです。
だからこそ、今後は資源を守りながら、適切に暮らしへ取り入れていくことが大切だといえるでしょう。
6.安価な製品と高級ラタン家具の違い
ラタン家具とひと口にいっても、価格帯は幅広く、数千円で手に入るものから、数十万円の高級品まで存在します。その違いはどこにあるのでしょうか。
まず大きな要素は「素材の質」です。ラタンにも種類があり、太さや繊維の密度によって耐久性が変わります。
高級品には均一で丈夫なラタンが選別され、節や割れが少ない部分だけを使用するのに対し、安価な製品では品質にばらつきのある素材が使われることも多いのです。
次に「加工と仕上げの精度」。ラタン家具は機械だけで仕上げることができず、多くの工程が職人の手作業に頼っています。
高級品では、一本一本の曲げや編み込みが丁寧で、編み目の隙間も美しく揃っており、見た目にも滑らか。
対して安価なものは、表面のささくれや編み込みの不均一さが目立ち、長年使ううちに歪みが出やすい傾向があります。
さらに「構造の強さ」も重要です。高級ラタン家具は芯材までしっかりと使い、フレームが堅牢に組まれているため、年月を経てもぐらつきにくい設計になっています。
一方、安価な製品は表面だけラタンを巻きつけ、内部を金属や安価な木材で補強していることも多く、軽く見えても耐久性には差が出ます。
つまり、価格の違いは単なるブランド料ではなく、素材の選別・職人技・構造設計といった「見えない部分の質」の差によるもの。長く使う家具として考えれば、初期投資は大きくても高品質なラタン家具の方が、結果的に暮らしに安心感を与えてくれるのです。
7.通気性の良さとカビ対策|お手入れの工夫
ラタン家具の魅力のひとつに「通気性の良さ」があります。
編み込まれた構造は空気を通しやすく、座ったときの蒸れを防ぎ、収納家具として使えば中の湿気を逃がす役割も果たします。特に夏場や湿度の高い時期には、自然素材ならではの快適さを実感できるでしょう。
ただし、天然素材であるラタンは湿度を吸いやすく、長時間風通しの悪い場所に置くとカビが発生することがあります。
例えば、脱衣所や洗面所など、常に湿気がこもる場所では注意が必要です。
こうした空間には、見た目がラタンに似た「ポリプロピレン製のラタン風家具」を選ぶのもひとつの方法。プラスチック素材は水に強いため、日常的に湿気が多い場所では実用的な選択肢になります。
もちろん、天然ラタンを楽しむ場合でも簡単なお手入れで十分に長持ちします。定期的に乾いた布やブラシでほこりを取り、時々風通しのよい場所に置くだけで、カビのリスクはぐっと下がります。梅雨時には扇風機や除湿機の風を軽く当てるのも効果的です。
自然素材を暮らしに取り入れるからこそ、少し手をかけてあげる。その時間すら心地よいひとときになるのが、ラタン家具の魅力でもあります。

8.軽さが生む利便性|年配の方にも優しい家具
ラタン家具の大きな魅力のひとつは「軽さ」です。掃除をするとき、椅子やラックを動かすのが重くて大変…そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
ラタン家具は驚くほど軽量で、椅子や小さなテーブルなら片手で持ち上げられるほど。掃除機をかける際にサッと移動させたり、来客に合わせてレイアウトを変えたりするのも気軽にできます。「軽い家具」というのは、日常のちょっとした動作を大きく楽にしてくれるのです。
この軽さは、特に年配の方にとって大きな安心感につながります。腰や膝に負担をかけずに家具を動かせるので、誰かに頼らずとも自分の暮らしを整えることができます。
たとえば、窓辺へ椅子を運んで朝日を浴びながら新聞を読む。あるいは、来客に合わせて座席を増やすために椅子を移動させる。ラタンなら体の負担を気にせず、その都度自由に暮らしを楽しむことができます。
一方で、軽い家具に対して「壊れやすいのでは?」と心配される方も少なくありません。
しかし、ラタンは細くても驚くほどの強度を持っています。繊維が縦横に絡み合っているため、しなやかで折れにくく、衝撃を受けても力をうまく分散させます。実際、同じ太さの木材よりも折れにくいとされ、椅子やソファのフレームにも安心して用いられてきました。
また、ラタン家具は「編む」という技術によってさらに強さを増しています。しっかりと編み込まれた構造は、全体で荷重を受け止める仕組みになっており、一部に負担がかかっても壊れにくいのです。
だからこそ、軽量でありながら長年使用に耐え、実際に数十年単位で愛用されている製品も珍しくありません。
「軽いのに丈夫」。この二つを両立しているのは、自然が育んだ素材の力と、職人の編みの技術があってこそ。ラタン家具は、暮らしを快適にし、年齢を重ねても安心して使える心強い存在なのです。
9.アジアンにも和にも、洋風インテリアにも馴染むデザイン
ラタン家具というと「アジアンリゾート」のイメージを思い浮かべる方も多いかもしれません。確かに南国のホテルやカフェでよく使われる素材ですが、その表情はとても幅広く、実は和室にも洋室にも自然に溶け込む懐の深さを持っています。
たとえば畳の部屋に置くと、竹や木のような自然素材との相性がよく、落ち着いた和の雰囲気を引き立てます。縁側にラタンの椅子を置けば、夏の夕暮れに風を感じながら涼む昔ながらの暮らしがよみがえるでしょう。
一方、洋風のリビングでは、編み目のデザインが空間に軽やかなリズムを生み、ナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれます。木材や布と合わせると温もりが増し、ガラスや金属と合わせればスタイリッシュにまとまります。
近年は直線的なデザインやモノトーンカラーのラタン家具も増え、北欧インテリアやシンプルモダンなお部屋にも違和感なく馴染むようになっています。
このように、ラタン家具は「素材感」と「編みのデザイン」によってさまざまな表情を見せてくれます。
アジアンリゾートの開放感も、和の静けさも、洋風の洗練も、ひとつの素材で叶えられるのは大きな魅力です。
暮らしのスタイルに合わせて自在に取り入れられる柔軟さこそ、ラタンが時代を超えて愛される理由なのです。

10.ラタン風のポリプロピレン家具との比較と選び方
近年人気が高まっているのが「ラタン風のポリプロピレン家具」です。見た目は本物のラタンによく似ていますが、素材は樹脂。天然ラタンと比べると、価格が手ごろで水や湿気に強く、屋外や脱衣所など湿度の高い場所でも安心して使えるのが大きな特徴です。
一方で、ポリプロピレンはあくまで人工素材。軽く丈夫ではあるものの、使い込むほどに艶や色合いが深まる「経年変化」を楽しむことはできません。触れたときの温もりや、編み目からこぼれる光の柔らかさといった、自然素材ならではの表情はラタンならではの魅力といえます。
選び方のポイントは、置く場所と用途を考えることです。
湿気がこもりやすい脱衣所やベランダにはポリプロピレン製を、リビングや寝室のようにくつろぎの時間を大切にしたい場所には本物のラタンを選ぶと、それぞれの特性を活かせます。また、天然ラタンを使う場合でも、時々風に当てて湿気を逃がすなど、少し手をかけることで長く快適に使えます。
本物のラタンと人工素材、それぞれに長所があります。大切なのは「どんな暮らし方をしたいか」を考えて選ぶこと。自然のぬくもりを日常に取り入れたいのか、実用性を優先するのか。
暮らしのスタイルに合わせて使い分けることで、より快適で心地よい空間をつくることができます。
11.まとめ|自然とともに暮らしを豊かにするラタン家具
ラタン家具は、昔はどこの家庭にもある身近な存在でした。しかし今では、資源の減少や職人技の希少性から、むしろ「選び抜かれた家具」として価値を高めています。
軽くて丈夫で湿気に強いという素材の特性は、掃除や模様替えを楽にし、年齢を重ねても無理なく暮らせる安心感をもたらします。
また、アジアンリゾートの雰囲気から和室の落ち着き、洋風インテリアのモダンな空気感まで、どんな空間にも自然に馴染む柔軟さも魅力です。
一方で、ラタン風のポリプロピレン家具など、人工素材の選択肢もあります。暮らしの場面に合わせて使い分けることで、それぞれのメリットを活かすことができます。自然の経年変化を楽しむか、実用性を重視するか。大切なのは「自分の暮らしに合った選び方」をすることです。
ラタン家具は、ただの生活道具ではなく、自然が育んだ素材と人の手仕事が生み出した特別な存在。エコを意識しながらも、心地よさや豊かさを暮らしに取り入れたい方にとって、長く寄り添ってくれる頼もしい家具といえるでしょう。
実店舗ではラタン家具の修理も承っています。
どうぞお気軽にご相談ください。







