
家具とカビの意外な関係
健康を守るために知っておきたいこと
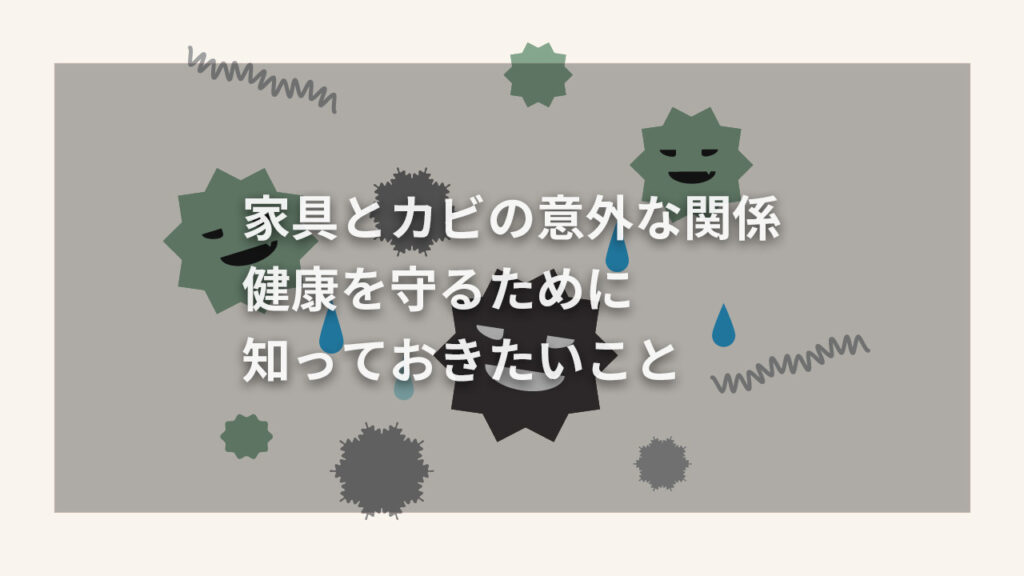
家具は暮らしを支える大切な存在ですが、その置かれる環境によっては思わぬ落とし穴が潜んでいます。
湿気の多い日本の住まいでは、カビと家具の関係を無視することはできません。
見た目にはきれいでも、気づかないうちに内部でカビが繁殖し、アレルギーや健康被害につながるケースも少なくありません。
特にMDF(中密度繊維板)を使った家具は手頃でデザイン性に優れる一方で、湿気をため込みやすく、住環境によってはカビの温床になることがあります。
実際に当店でも、引き取りの際にベッドがカビだらけになってしまった例を目にしたことがあります。
家具は単なるインテリアではなく、毎日身体が触れるものだからこそ、見えない部分の清潔さは軽視できません。
特に寝具やベッドまわりのカビは、快適さだけでなく安心・安全な暮らしを守るうえでも大きなポイントになります。
一方で、天然木の家具には素材が持つ調湿性や耐久性があり、手入れ次第で長く健やかに使うことができます。
この記事では、家具とカビの関係や健康リスクを整理しながら、素材による違いを見直すきっかけをお伝えします。
家具選びの参考になれば幸いです。
1.家具とカビ ― なぜ発生するのか
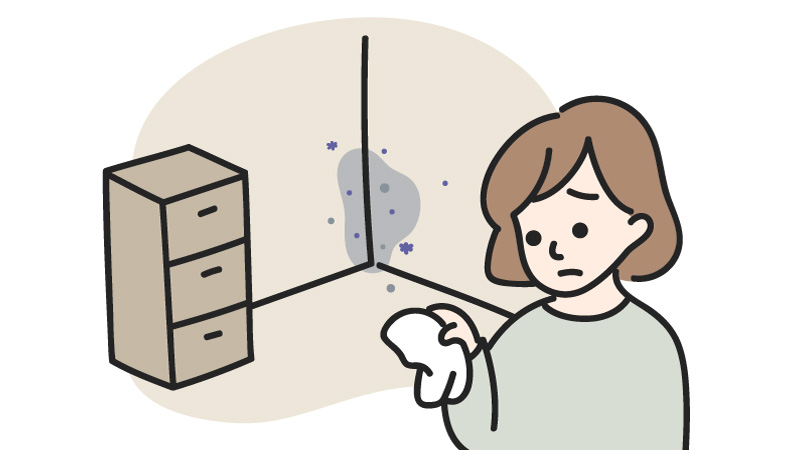
カビと聞くと、まずお風呂場やキッチンを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、私たちが日常的に使っている家具もまた、カビが好む条件がそろいやすい場所のひとつです。
特に湿気の多い日本の気候では、家具の素材や置き方によっては、気づかないうちにカビが広がってしまうことがあります。
カビは微生物の一種で、温度・湿度・栄養源がそろうと急速に繁殖します。
一般的に気温20~30度、湿度70%前後になると活発に増え始めると言われています。
夏の梅雨時期はもちろん、冬でも結露が発生する室内では条件が整いやすく、油断できません。
そして家具に使われる木材や繊維は、カビにとって栄養源となる有機物です。
さらに、ベッドやソファといった家具は人の汗や皮脂が付着するため、栄養分はより豊富になり、繁殖を後押ししてしまいます。
もうひとつ見落としがちなのが「通気性」です。
家具を壁にぴったりつけて置いたり、床との隙間が少ないタイプを選んだりすると、湿気がこもりやすくなります。
空気が動かない環境はカビの大好物。
とくにベッド下やタンスの裏側など、普段掃除のしにくい場所ほど、気づかないうちにカビが広がっていることがあるのです。
このように考えると、家具とカビの関係は特別なことではなく、「どの家庭でも起こりうる現象」だとわかります。
だからこそ、「なぜカビが生えるのか」を理解しておくことが、健康で快適な住まいを守る第一歩になります。
「家具は長く使うものだからこそ、清潔に保ちたい」「家族が安心して過ごせる環境を整えたい」――多くの方がそう願っていると思います。
その気持ちに寄り添うと、家具にカビが生える仕組みを知っておくことは、決して専門的な知識ではなく、日々の暮らしに直結する大切な知恵だといえるでしょう。
2.MDF製家具とカビのリスク

家具の素材にはさまざまな種類がありますが、その中でも近年よく使われているのがMDF(中密度繊維板)です。
木材を細かい繊維にして接着剤で固めた人工素材で、加工がしやすく、コストも抑えられるため、多くの量産家具に利用されています。
デザイン性も高く、一見すると無垢材の家具と見分けがつかないほどきれいに仕上げられています。
しかし、この便利なMDFには湿気に弱いという特性があります。
繊維をぎゅっと圧縮しているため、表面が一度水分を吸ってしまうと乾きにくく、内部に湿気をため込んでしまうのです。
日本のように湿度の高い環境では、この「乾きにくさ」がカビの温床となります。
さらにMDFには、木の繊維を固めるために接着剤や樹脂が使われています。
これらは時間が経つと劣化し、微細なひび割れや隙間が生まれます。
そこに湿気が入り込むと内部でカビが発生し、外からは見えにくい部分で静かに広がっていくことがあります。
表面を拭いただけでは落としきれないカビが、内部に根を張ってしまうケースもあるのです。
実際に当店で家具を引き取った際、ベッドのフレームや収納家具がカビで真っ白になっていた例がありました。
見た目はきれいに使われているようでも、分解してみると内部までカビが浸食していることも珍しくありません。
特にベッドは人の体温や汗を日常的に受け止めるため、MDF素材だとカビのリスクが一層高まります。
もちろん、MDF製の家具がすべて悪いわけではありません。
価格やデザインの選択肢が豊富で、多くの家庭に取り入れやすい利点もあります。
ただ、その特性を知らずに使ってしまうと、「思ったより早く傷んでしまった」「カビで処分せざるを得なくなった」といった後悔につながる可能性があるのです。
家具は毎日を共にする存在だからこそ、素材の違いを知っておくことはとても大切です。
「手頃だから選ぶ」だけでなく、「住環境や健康への影響」まで考えてみることで、より安心して暮らせる家具選びにつながります。
3.カビが人体に及ぼす影響

カビは自然界に広く存在する身近な存在です。
土の中や空気中にも常に漂っていて、私たちは普段から少量のカビの胞子を吸い込んで暮らしています。
つまり「カビを完全になくすこと」は難しく、共存しているのが現実です。
ただし、家具や寝具などに大量のカビが発生すると、体への負担が無視できなくなることがあります。
まず知っておきたいのは、アレルギーとの関係です。
カビの胞子は空気中に舞い上がりやすく、これを長期間吸い込むことで、くしゃみや鼻水、咳といった症状が出る人がいます。
特にアトピー性皮膚炎や喘息を持つ方、小さなお子さまや高齢の方は影響を受けやすいとされています。
必ずしも全員に症状が出るわけではありませんが、「体質によっては不調のきっかけになる」という点は覚えておくとよいでしょう。
また、寝室まわりにカビが広がると、睡眠の質にも影響を与える可能性があります。
カビ臭さを感じる環境で眠ると無意識にストレスとなり、深い眠りを妨げてしまうこともあります。
ベッドやマットレスにカビが発生すると、目には見えなくても胞子が枕元に届きやすいため、毎日の快適さを左右する大きな要因になりかねません。
大切なのは、こうした影響を過剰に恐れるのではなく、「家具や部屋の環境を整えることで防げる」という視点を持つことです。
例えば通気性を確保したり、湿度を管理したりするだけでも、カビのリスクはぐっと減らすことができます。
さらに素材によっては、湿気をため込みにくく、清潔に保ちやすい家具もあります。
カビは誰の暮らしにも身近にあるからこそ、「体にどんな影響があるのか」を少し知っておくだけで、日常の工夫や家具選びのヒントになります。
安心して過ごせる環境を整えるための一歩として、カビと健康の関係を意識してみるのは、とても意味のあることだと思います。
4.家具屋としての体験談

家具屋という仕事をしていると、お客様のご依頼で古い家具を引き取る機会も少なくありません。
その中で印象的だったのが、あるお客様からお預かりしたベッドフレームにカビが広がっていた例です。
見た目はそれほど傷んでいなかったのですが、分解してみると裏側や板の合わせ目に白いカビが点々と残っていて、私たちも驚きました。
ただ、その家具を使っていたご家庭は決して不衛生にしていたわけではありません。
むしろ丁寧に暮らされていて、家具もきれいに保たれていました。
それでも、部屋の構造や立地、湿気の多い季節などが重なり、気づかぬうちにカビが繁殖してしまったのだと思います。
つまり、誰にでも起こりうることなのです。
このような経験をすると、「家具と環境との相性」という視点がとても大切だと実感します。
どんなに大事に扱っていても、素材や設置場所によっては湿気をため込みやすいことがありますし、その逆に風通しが良い環境や素材を選ぶことで、長く清潔に使えることもあります。
私たち家具屋は数多くの事例に触れる立場だからこそ、こうした実体験をお伝えすることも役割だと思っています。
決して恐れる必要はありませんが、「家具も暮らし方や住まいの環境と一緒に考えるもの」だと知っていただければ、より安心して快適に過ごしていただけるはずです。
5.天然木のよさとカビへの強さ

家具の素材として昔から使われてきた天然木には、人工的に作られた板材とは違う魅力があります。
そのひとつが、木そのものが持つ調湿作用です。
木は伐採された後も呼吸を続けており、空気中の湿気を吸収したり放出したりしてバランスを取ろうとします。
いわば「天然の湿度調整機能」が備わっているのです。
この働きのおかげで、湿気がこもりにくく、結果的にカビの発生を抑える効果が期待できます。
さらに天然木の表面には、樹種によって独自の成分が含まれています。
たとえばヒノキや杉に含まれるフィトンチッドは、森林浴でも知られるように、リラックス効果をもたらすと同時に、カビや細菌の増殖を抑える働きがあると考えられています。
こうした成分が直接的に家具を「抗菌仕様」にするわけではありませんが、木材が本来持つ力として私たちの暮らしを支えてくれているのです。
もちろん天然木も、まったくカビが生えないわけではありません。
風通しの悪い場所に長期間置けば、表面にカビがつくことはあります。
ただし、表面を拭き取ったり磨いたりすることで比較的簡単にきれいに戻せる点が特長です。
内部まで湿気を閉じ込めやすいMDFと比べると、扱いやすく、長く清潔に保ちやすいと言えるでしょう。
また、天然木の家具は年月を重ねるほどに味わいが増し、多少の傷やシミさえも暮らしの歴史として楽しめるという側面があります。
日々の手入れを続ければ、世代を超えて使い継ぐことも可能です。
カビのリスクを減らしながら、長い目で見て持続的に愛用できる点は、大量生産の素材にはない大きな魅力です。
こうした特徴を知ると、天然木家具は単なる「見た目の良さ」以上の価値を持っていることに気づきます。
快適さや安心感を長く保ちたい方にとって、天然木は頼もしい選択肢のひとつになるでしょう。
関連商品
6.まとめ ― 家具屋として伝えたいこと
家具屋という立場で日々多くの商品に触れていると、素材やつくりの違いによって、暮らしの快適さが大きく変わることを実感します。
もちろん、どの家具にも良さがあり、ライフスタイルやご予算によって選択肢はさまざまです。
ですが、湿気に強いかどうか、長く清潔に使えるかどうか、といった視点を加えると、家具はただの「物」ではなく、暮らしを支える大切な相棒としての存在感を増していきます。
私たちがこれまで見てきた事例の中には、思わぬカビの被害で家具を手放さざるを得なかったケースもありました。
一方で、天然木の家具を丁寧に手入れしながら、長く愛用されているご家庭にも出会ってきました。
そこには、単なる素材の違い以上に、「家具と暮らしを大事にする」という考え方が反映されているように思います。
家具は毎日目にし、手に触れるものだからこそ、心地よさや安心感が生活の質に直結します。
私たち家具屋が伝えたいのは、「こう選ぶべき」という答えではなく、「家具選びにはこんな視点もある」ということです。
その気づきが、皆さまの暮らしを少しでも豊かにし、長く健やかに支えるきっかけになればうれしく思います。

