
夏休みの自由研究や工作に!組手什で遊んで学べる木工時間
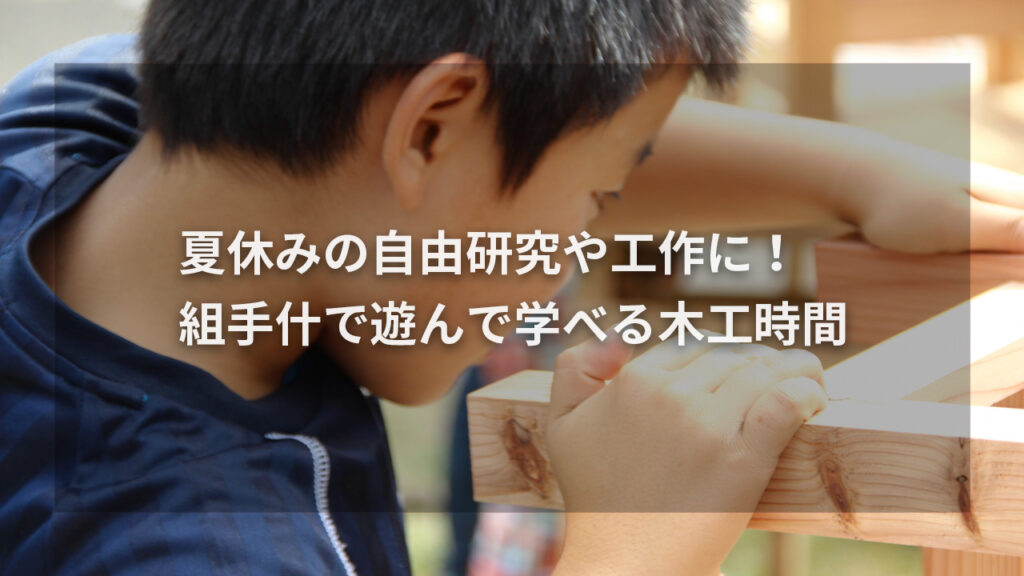
長いようであっという間に過ぎてしまう夏休み。
「せっかくの時間を、何か心に残ることに使えたら」――
そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか?
プールにお出かけ、おうちで映画、おばあちゃん家への帰省……どれも夏の思い出には欠かせないイベントですが、今年はちょっとだけ、“学び”や“体験”にも目を向けてみませんか?
おすすめしたいのが、「組手什(くでじゅう)」という木製のDIYキット。
鳥取・三重・岡山の森で育った杉の間伐材を使っていて、道具いらず、木の溝をはめ込むだけで棚や小物スタンドなどを作ることができるんです。
親子で一緒に手を動かしながら「どうやって作る?」「これに使えるかも!」と考える時間は、ものづくりの楽しさはもちろん、自然や環境への興味を育むきっかけにもなります。
今、学校でも「SDGs」や「環境問題」を学ぶ機会が増えてきています。
だからこそ、こうした“リアルな体験”が、自由研究や夏の学びとしてもとても価値あるものになるのです。
今年の夏は、ただ「作る」だけじゃない、“未来につながる自由研究”にチャレンジしてみませんか?
木の香りに包まれながら、親子で夢中になれる時間が、きっと特別な思い出になります。
1.はじめに|夏休みの自由研究、もう決まった?

夏休みが近づくと、毎年のように悩むのが「自由研究、今年はどうしよう?」というテーマ選び。
特に小学生のお子さんがいるご家庭では、「なるべく楽しみながらできて、できればちょっと学びにもつながるものを…」と、親のほうが頭を悩ませてしまうこともありますよね。
自由研究は、子どもが自分で考え、調べ、手を動かしてまとめる貴重な機会。
けれど、それが“宿題”としてプレッシャーになってしまっては本末転倒です。
どうせなら、親子で一緒に楽しめて、思い出にもなるようなテーマを選びたいものです。
そんな方にぜひ知っていただきたいのが「組手什(くでじゅう)」という木のDIYキットです。
聞き慣れない名前かもしれませんが、実はこれ、環境にやさしい国産の杉材を使った、子どもでも扱いやすいアイテム。
組み立ては工具も釘もいらず、木の溝を“組む”だけで、棚や小物入れなどが簡単に作れてしまう優れものなんです。
自由研究のテーマとしても、「木材のことを調べる」「組手什で作ったものを記録する」「間伐材や森の役割についてまとめる」など、さまざまな切り口があるのが魅力。
夏の思い出づくりと学びを両立できる、そんなアイテムとして注目が集まっています。
2.組手什(くでじゅう)ってなに?

「組手什(くでじゅう)」という名前、聞いたことがありますか?
ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとてもシンプルで、親子で楽しめる木製のDIYキットです。
「什(じゅう)」とは、もともと“道具を入れる箱”という意味を持つ古い言葉。
そして「組手」は、木材に加工された溝と溝を噛み合わせて、釘や接着剤を使わずに組み立てる方法のこと。
この2つが組み合わさって、「組手什」と名付けられました。
見た目は細長い木の板。
そこに互い違いに溝が入っていて、それをはめ込むことで棚や収納グッズなどが作れる仕組みです。
しかも使われている木材は、鳥取県・三重県・岡山県などで伐採された杉の間伐材。
国内の森林から生まれた、環境にやさしい素材なのです。
間伐材とは、成長の過程で密集しすぎた木々の一部を間引いた際に出る木材のことです。
森を健やかに保つためには必要な作業なのですが、こうして伐採された木が有効に使われず、廃棄されるケースも少なくありません。
そんな“もったいない”を解決するのが、この組手什。
森を守りながら、資源を無駄なく活かせる素晴らしい取り組みです。
また、組手什の魅力は“つくる楽しさ”にもあります。
溝同士を組み合わせるだけなので、小学生でも簡単に扱えますし、棚やラック、小物入れ、スマホスタンドまで、アイデア次第でいろいろなものが作れます。
何を作ろうか考える時間も、親子で一緒に手を動かす時間も、どちらもきっと忘れられない体験になるでしょう。
「DIYって難しそう」「工具を使うのはちょっと心配…」というご家庭にも安心。
組手什は、ネジも金具も使わずに組み立てられるため、安全性が高く、木の感触や香りを感じながら作業できる点もポイントです。
まるで“木のパズル”のように楽しめて、インテリアとしても実用的な作品ができあがります。
さらに、完成した作品は“作って終わり”ではなく、暮らしの中で実際に使うことができます。
自由研究としてはもちろん、「子ども部屋の収納棚に使ってみる」「おもちゃを片づける箱として活用する」など、日常の中での活躍シーンもたくさん。
自分で作ったものを毎日使う体験は、子どもにとって大きな自信にもつながります。
「木を組んで、自由に形をつくる」
そんなシンプルだけれど奥深い体験が、組手什には詰まっています。
3.なぜ今「間伐材」なのか?|森と暮らしのつながり

私たちの暮らしにとって、木はとても身近な存在です。
家具や建材、紙、割り箸など、日常の中にはたくさんの「木」が使われています。
でも、その木がどこから来て、どんな役割を果たしているのか、意外と知らないことが多いものです。
組手什に使われている杉は、「間伐材」と呼ばれる木材です。
これは、森の中で木が密集しすぎて育ちにくくなったときに、不要な木を間引くことで生まれる副産物のようなもの。
つまり、“森を元気にするために、あえて伐る”ことで得られる資源なのです。
本来、森には日光や風が通り抜け、木がしっかり根を張って大地を支える必要があります。
でも、手入れされずに放置された人工林では、木が込み合って光が届かず、地面がやせ細り、水も空気も通りにくくなってしまいます。
その結果、木は細く弱くなり、台風や大雨で土砂災害が起きやすくなるのです。
間伐は、そんな森林を健全に保つために欠かせない大切な作業です。
そして、その間伐で出た木を捨てずに活用するのが、今、地球環境を守るための大きな一歩とされています。
ところが、間伐材はふつうの木材よりも価値が低く見られがちで、使われずにそのまま放置されてしまうことも少なくありません。
「使い道がない」と思われがちな間伐材ですが、実は軽くて加工しやすく、温かみのある手ざわりが魅力。
組手什のような製品に生まれ変わることで、自然の恵みを無駄にせず、暮らしにやさしく取り入れることができるのです。
また、国産の間伐材を使うことは、私たちの生活と“森の健康”をつなぐ架け橋でもあります。
海外の安価な木材ではなく、日本の山で育った木を使うという選択は、地元の林業や職人さんたちを応援することにもつながり、地域経済の循環にも貢献します。
組手什を通じて、親子で木に触れ、木の生まれた場所や意味を知る。
それは「作って楽しい」だけでは終わらない、未来につながる学びになるはずです。
4.組手什の魅力と可能性|親子で広がるDIY体験

組手什の最大の魅力は、なんといっても“自由につくれる楽しさ”にあります。
あらかじめ決められた形を作るのではなく、木のパーツを組み合わせながら、自分だけの形や使い道を考えていけるのがポイント。
発想しだいで、小さな本棚やスマホスタンド、キッチン収納など、実用的なアイテムがどんどん生まれます。
組み立てはとてもシンプル。
杉材の板にはあらかじめ溝が切られており、それをはめ込むだけで形ができあがります。
工具や接着剤を使わないため、小学生のお子さんでも安全に取り組めるのが嬉しいところ。
保護者がそばにいれば、幼児のお子さんでも一緒に“木を組む”体験ができます。
完成した作品は「飾って終わり」ではなく、実際に日常で使えるものばかり。
おもちゃを入れる棚や、机の上の小物収納など、子どもの身近な空間にすっとなじむデザインも魅力です。
自分で作ったものを使い続けることで、物を大切にする気持ちや「つくる→使う→直す」の循環も自然と身についていきます。
また、親子で一緒に手を動かす時間は、会話のきっかけにもなり、普段とは少し違った関係性を築けるチャンスでもあります。
試行錯誤しながら形をつくる過程には、小さな「成功体験」や「達成感」がたくさん。
完成したときの子どもの表情には、きっと満足と誇らしさがあふれるはずです。
「つくる楽しさ」と「自然素材のぬくもり」、そして「環境への優しさ」。
そのすべてが詰まった組手什は、夏休みの自由研究やものづくり体験にぴったりの素材です。
5.SDGsの観点から見た組手什

「SDGs(エスディージーズ)」という言葉を、最近よく耳にするようになりました。
これは“持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)”の略で、国連が2030年までに達成すべきと定めた17の目標のこと。気候変動、貧困、教育、エネルギー、資源の有効活用など、さまざまな課題に取り組むための国際的な共通ルールです。
実は、組手什のような木製キットも、このSDGsの視点から見るととても意義のある取り組みだとわかります。
特に関係の深いのが、以下の3つの目標です。
▶︎ 目標12「つくる責任、つかう責任」
安くて便利なモノがあふれる今の時代ですが、「何を買い、どう使い、どう手放すか」は、私たち一人ひとりに問われています。
間伐材は、森林整備の際に出る副産物で、見た目や質のばらつきから商品としては敬遠されがちでした。ですが、組手什のようにその木を“ちゃんと使い切る”ことは、資源の有効利用や無駄の削減につながります。限られた資源を最後まで使い切る姿勢こそ、SDGsの目指す「責任あるものづくりと消費」の具体的な実践です。
▶︎ 目標13「気候変動に具体的な対策を」
地球温暖化が進む中で、森林が果たす役割はますます重要になっています。木は大気中のCO₂を吸収してくれる“自然のフィルター”のような存在。ところが、管理されていない人工林はCO₂の吸収力が弱まり、逆に災害のリスクを高めてしまいます。
間伐は、木と木の間に光や風を通し、健康な森に育て直す大切な作業。その際に出た木材を活用することは、森を守る活動を支えることにもつながります。組手什を通じて間伐の意味を知ることは、気候変動への理解を深めるきっかけになるのです。
▶︎ 目標15「陸の豊かさも守ろう」
豊かな森は、土砂崩れなどの災害を防ぐだけでなく、多くの動植物のすみかでもあります。間伐された森は、光が入り、下草が育ち、昆虫や鳥たちも戻ってきます。人の手で手入れされた森は、自然の多様性を守り、未来へとつないでいくための大切なフィールド。
組手什の素材である杉の間伐材を使うことは、その森の再生と生物多様性の保護に、ほんの少しでも貢献することになります。小さなアクションかもしれませんが、家庭の中でそうしたことを体験することで、子どもたちの意識は確実に変わっていきます。
SDGsは決して「大人の世界だけの話」ではありません。
むしろ、未来を生きる子どもたちにこそ、自分ごととして知ってほしいテーマです。
「木を使う」=「自然を壊す」ではなく、
「自然とつながる」ことになる——
そのことを、組手什はやさしく教えてくれます。
楽しくて、役に立って、未来のことも考えられる。
そんな体験ができる組手什は、まさに夏休みの自由研究にぴったりのアイテムです。
6.当店で扱っている組手什の紹介
ここで、当店取り扱いの組手什の中から、親子で組み立てを楽しめるキットを厳選しておすすめします。
7.まとめ|自由研究が「未来を考える時間」に

毎年やってくる夏休みの自由研究。今年は“環境”や“ものづくり”に目を向けてみませんか?
組手什は、親子で楽しめるDIYキットであると同時に、間伐材という地球にやさしい資源を活かした、サステナブルな取り組みでもあります。
木のぬくもりを感じながら手を動かし、完成した作品を実際に使うことで、「作って終わり」ではない、暮らしに根づいた学びが生まれます。
また、SDGsや森林保全といった大きなテーマも、組手什というシンプルな木の道具を通じて、ぐっと身近に感じられるはずです。
「森ってどうして必要なんだろう?」
「木を使うことは悪いこと?」
そんな疑問を親子で一緒に考える時間こそが、今、最も価値のある“自由研究”なのかもしれません。
自然を大切にすること、資源を無駄にしないこと、そして自分の手で何かを生み出す喜び。
組手什は、そのすべてを体験させてくれる、小さくて、大きな学びのきっかけです。
-
 よみもの
よみもの
「長く使える机を、子どもに。」杉工場が届ける木のぬくもり
天然木のやさしさと職人の技が息づく杉工場の家具。子どもの学習机から大人のワークデスクまで、暮らしに寄り添いながら長く使える魅力を紹介します。 -
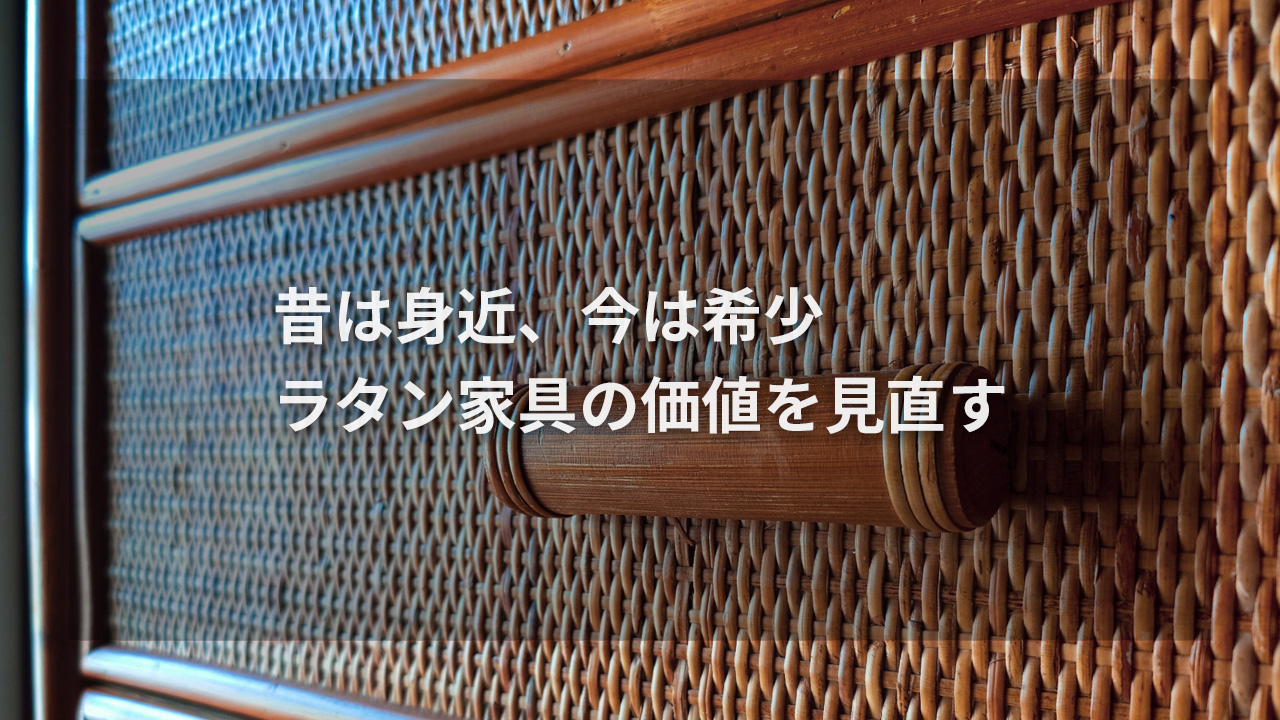 よみもの
よみもの
昔は身近、今は希少|ラタン家具の価値を見直す
ラタン家具は懐かしくも新しい存在。エコで快適、和洋を問わず馴染む自然素材の魅力を、暮らしに寄り添う家具屋の視点からお届けします。 -
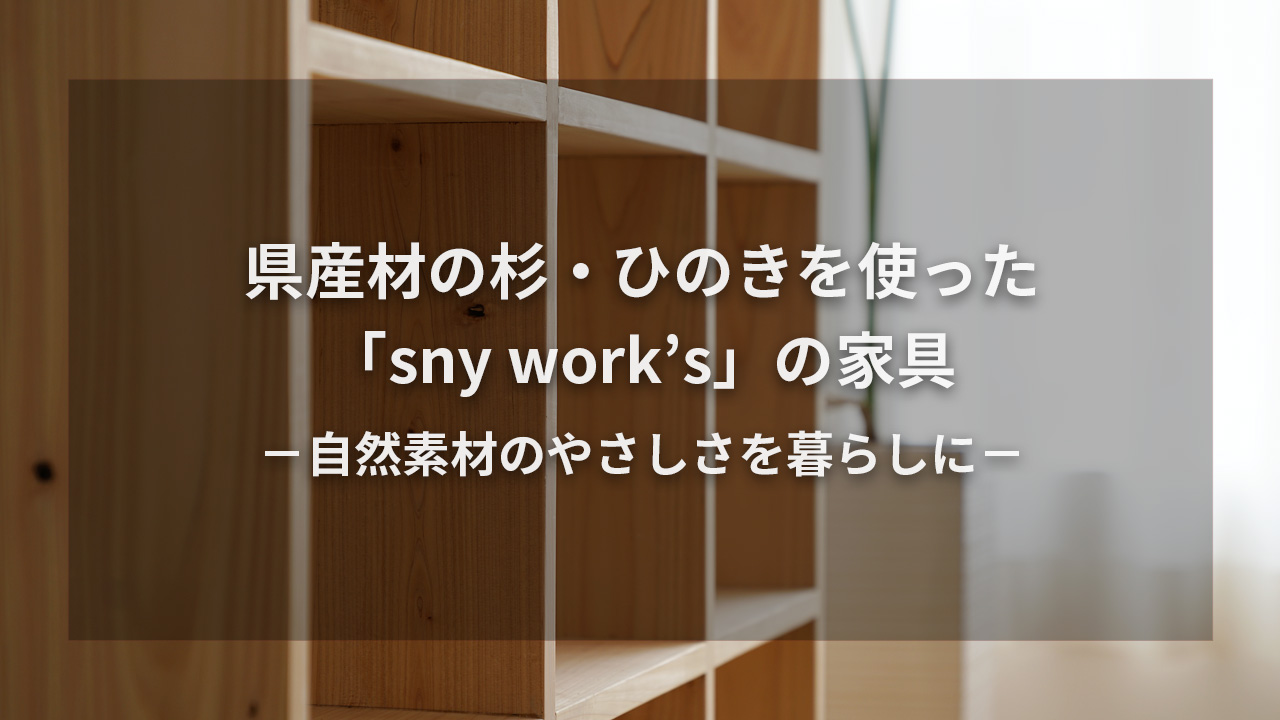 よみもの
よみもの
県産材の杉・ひのきを使った「sny work’s」の家具|自然素材のやさしさを暮らしに
国産木材を使い、化学物質に頼らず仕上げた sny work’s の無垢家具。長く使える安心感と自然素材の心地よさを暮らしに。



